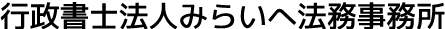はじめに
社会福祉法人とは非営利の一つで「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されている、公益性の高い民間企業の一つです。
社会福祉法人は、税の優遇、助成金・補助金がうけられるというメリットがあります。しかしながら、社会福祉法人を設立することは簡単にはできません。設立するための役員は、人数が決まっており、要件を満たしたものでしか役員になれません。また多くの資産も必要です。
社会福祉法人が行うことのできる事業
社会福祉事業(第一種・第二種)、公益事業、収益事業の3種に分けられます。
◇ 第一種社会福祉事業
利用者の保護の必要性が高い事業を行っているため、経営が安定していなければなりません。また利用者への影響が大きい社会福祉事業のため、国、地方公共団体、社会福祉法人のいずれかでなければ運営できません。株式会社や合同会社などは運営できません。
- 救護施設
- 更生施設
- 授産施設
- 生活困難者に対して助葬を行う事業
- 乳児院
- 児童養護施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 障害者支援施設
など
◇ 第二種社会福祉事業
第二種社会福祉事業は、比較的利用者への影響が小さいため公共規制の必要性が低い事業のことをいいます。原則、社会福祉法人ではなくでも、すべての主体が届け出をすれば、事業経営が可能です。
- 保育所
- 放課後児童健全育成事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 障害児通所支援事業
- 母子家庭等日常生活支援事業
- デイサービス事業
- 認知症対応型老人共同生活援助事業
- 小規模多機能型居宅介護事業
- 障害福祉サービス事業
- 移動支援事業
- 一般及び特定相談事業
など
◇ 公益事業
有料の老人ホーム運営など、公益を目的とする事業であり、社会福祉事業以外の事業のことをいいます。
当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げてはならず、社会福祉と無関係なものを行うことは認められません。公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てなければなりません。
<公営事業の例>
- 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポ-ツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業
- 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 子育て支援に関する事業
- 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- ボランティアの育成に関する事業
- 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 社会福祉に関する調査研究等
“「社会福祉法人の認可について」(平成28 年11 月11 日 局長通知 一部抜粋)”より
◇ 収益事業
貸しビル、駐車場、公共的な施設内の売店の経営など福祉事業の妨げとならないような事業のことをいいます。収益事業は以下の要件を満たす必要があります。
- 法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。
- 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。
- 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。
- 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
- 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。
- 母子及び寡婦福祉法第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令第6条第1項各号に掲げる事業については、3.は適用されないものであること。
“「社会福祉法人の認可について」(平成28 年11 月11 日 局長通知 一部抜粋)”より
社会福祉法人の設立要件
◆ 役員
7名以上の評議員と6名以上の理事と2名以上の監事が必要です。
評議員
- 評議員の数は理事の員数を超える数、つまり7名以上必要です。
- 評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有するもの」のうちから選任しなければなりません。
- 当該社会福祉法人の理事、監事、会計監査人、理事を兼任することはできません。
理事
- 6名以上の理事が必要です。
- 親族等特殊の関係があるもの(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)が一定数を超えてはいけません。
- 理事のうちには、必ず以下の要件をもつ者を含まなければなりません。
①社会福祉事業の経営に関する識見を有するもの
②その事業の区域における福祉に関する実情に通じているもの
③施設を設置して管理している場合には、その施設の管理者
監事
- 2名以上の監事が必要です。
- 監事のうちには、必ず以下の要件をもつ者を含まなければなりません。
①社会福祉事業について識見を有する者(社会福祉に関する教育、研究を行う者など)
②財務管理について識見を有する者(公認会計士、税理士など) - 当該社会福祉法人の理事、評議員、職員を兼任することはできません。
- 当該社会福祉法人に係る顧問税理士、顧問会計士、社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者であってはなりません。
◆ 資産
基本財産とその他財産、公益事業用財産、及び収益事業用財産が必要です。
基本財産
社会福祉事業を行うために必要な土地、建物等の資産のことをいいます。建物に関しては、融資や補助金など、活用できる制度があります。
その他財産
施設運営に必要な資産のことです。法人設立に際しては、施設の年間事業費の12分の1以上に相当する額を準備しておく必要があります。
公益事業用財産
公共事業の用に供する財産のことです。他の財産と分けて管理する必要があります。
収益事業用財産
収益事業の用に供する財産のことです。他の財産と明確に分離して管理する必要があります。
社会福祉法人設立の流れ
1. 定款作成
社会福祉法人を設立する際には、「定款(ていかん)」を必ず作成する必要があります。「定款」とは法人の成り立ちや運営において基本的規則をまとめたものです。記載事項には「必要的記載事項」と「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。
<絶対的記載事項>
必ず記載しなければなりません。1つの事項でも抜けていると、定款自体が成立しません。
- 目的
- 名称
- 社会福祉事業の種類
- 事務所の所在地
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 評議員会を置く場合には、これに関する事項
- 公益事業を行う場合には、その種類
- 収益事業を行う場合には、その種類
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法

2. 所轄庁の認可申請
定款作成後、所轄庁である都道府県知事または指定都市、もしくは中核市の長の認可を受ける必要があります。

3. 設立登記
設立の認可がされますと、認可されたことを証明する書類が送付されます。書類到達から2週間以内に、以下の事項を記載して管轄法務局に設立登記の申請を行います。
- 目的及び業務
- 名称
- 事務所住所
- 代表権を有する者の氏名、住所および資格
- 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
など